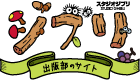ページ内容
2006年1月12日
第十六回 スタッフの共感
このところ原画がどんどん上がってきて、
キャラクターが形になるにしたがって気づいたことがあります。
キャラクターが、特に主人公のアレンとヒロインのテルーが、
“生っぽく”なってきているのです。
これは、作画スタッフの主人公の少年やヒロインに対する理解や共感が、
さらに深まってきているからだと、私は思います。
生きていくことの意味を求めても見つからず
心に闇を育てる少年アレンと、
生かされていることそれ自体の喜びを知り
それを少年に伝えようとする少女テルー。
意識的か無意識的かはわかりませんが、
スタッフのふたりへの理解が理屈を超えた実感へと変わって、
それが絵に反映されているように思うのです。
たとえば、ふっと目をそらすところや呆然とたたずんでいるところ。
そんな、ささいな表情やしぐさが妙に生っぽく見えてきたのです。
さらに、それはキャラクター全体の描き方にも表れてきています。
これもたとえを挙げると、アレンと旅するハイタカの描き方が、
「アレンから見たハイタカ」になってきているのです。
どこか、アレンと自分を重ねることで、
そういう描き方になってきたのではないでしょうか。
前回、声をつけることで、そのキャラクターが、
自分の思い描いていた存在を超えていく喜びについて描きました。
それは、作画についても同じなのです。
ストーリーがそうなっているというだけではもちろんダメで、
監督である私ひとりが登場人物を理解し、共感していても、
その映画は力を持ちません。
スタッフ一人ひとりの思いをこめた仕事こそが、
登場人物に命を宿らせることができる、
そう実感している今日この頃です。